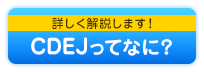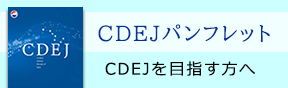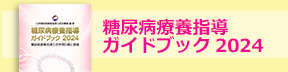| 標準学習時間 | 1.5時間~2時間程度 ※ 動画視聴2~3回/設問解答/コースレビュー回答の時間を想定 |
| 認定単位数 | <第2群>1単位 |
| 受講料 |
3,520円(税込) ※2020年4月お申込み分より改定しました。
|
| 受講期間 | 4ヵ月間 |
- 単位数・受講料・受講期間は一律です。
- 受講申込みについては、こちらをご覧ください。
- タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
- Jスキルコースは「単位の取れるeラーニング」です。更新要件で受講必須の講習とは異なります。
更新要件で受講必須の講習についてはこちらをご覧ください。
コース一覧
・「糖尿病患者における高血圧管理(講師:片山茂裕)」「糖尿病の脂質異常症管理(講師:石橋俊)」が3月31日をもって公開終了となります。
※「糖尿病腎症の診断と治療」をご担当の古家大祐先生におかれましては、2023年7月ご逝去の由承り 謹んで感謝と哀悼の意を表します。
高齢者糖尿病の療養指導(講師:荒木 厚)2018年11月公開01.
高齢者糖尿病の薬物療法(講師:深野 光司)2018年11月公開
糖尿病足病変の病態・診断・治療(講師:渥美 義仁)2019年5月公開
血糖コントロールの指標と目標値(講師:佐藤 麻子)2019年5月公開
糖尿病患者のフットケアの基本(講師:加藤 理賀子)2019年5月公開
糖尿病患者における高血圧管理(講師:片山 茂裕)2019年7月公開 ※2024年3月31日公開終了 →詳細はこちら
糖尿病の脂質異常症管理(講師:石橋 俊)2019年7月公開 ※2024年3月31日公開終了 →詳細はこちら
カーボカウントのポイント 基礎編/応用編(講師:黒田 暁生)2019年9月公開
2型糖尿病におけるインスリン治療 -患者背景を考慮したオーダーメイド治療-(講師:吉岡 成人)2019年12月公開
糖尿病腎症の診断と治療(講師:古家 大祐)2019年12月公開
糖尿病運動療法のアート(その1)(講師:天川 淑宏)2020年1月公開
2型糖尿病と服薬アドヒアランス(講師:堀井 剛史)2020年1月公開
糖尿病注射薬の療養指導 -自己注射指導のプラクティス1-(基礎編)(講師:朝倉 俊成)2020年2月公開
経口血糖降下薬治療(講師:田尻 祐司)2020年2月公開
J-DOIT3から学ぶ2型糖尿病の治療戦略(講師:門脇 孝)2020年2月公開
SMBG・CGMの活用法(講師:西村 理明)2020年4月公開
食品交換表に基づいたカーボカウント法(講師:高橋 徳江)2020年5月公開
糖尿病の食事療法(講師:本田 佳子)2020年8月7日公開
糖尿病治療における運動療法の意義と療養指導の在り方(講師:細井 雅之)2020年11月公開
糖尿病足病変の爪や皮膚のケア(基礎編/実践編)(講師:鈴木 由加)2021年9月公開
糖尿病網膜症(眼科医の立場から)(講師:北野 滋彦)2022年2月公開
日常診療で行う糖尿病性神経障害の診断と治療(講師:成瀬 桂子)2022年3月公開
糖尿病と神経精神疾患(講師:佐倉 宏)2022年4月18日公開
糖尿病性腎症の食事療法(講師:市川 和子)2022年7月22日公開
糖尿病とがん(講師:大橋 健)2023年4月19日公開
糖尿病運動療法のアート(その2)(講師:天川 淑宏)2023年5月24日公開
糖尿病治療の現状と問題点(体の仕組みから考える)(講師:植木 浩二郎)2023年6月27日公開
糖尿病合併妊娠(講師:荒田 尚子)2023年6月27日公開
コース詳細
※講師所属は、コース制作時点のものです。
高齢者糖尿病の療養指導
講師
荒木 厚(東京都健康長寿医療センター 内科総括部長(糖尿病・代謝・内分泌内科))
・1983年 京都大学医学部卒業、同附属病院老年科 研修医
・1984年 静岡労災病院(現 浜松労災病院)内科 研修医
・1985年 京都大学医学部大学院
・1987年 東京都老人医療センター内分泌科 医員
・1995-1996年 英国ロンドン大学ユニバーシティカレッジ/米国ケースウエスタンリザーブ大学留学
・1997年~ 東京都老人医療センター(現 東京都健康長寿医療センター)内分泌科復職、以後内分泌科 医長・同内分泌科 部長、糖尿病・代謝・内分泌内科 部長を歴任
・2012年より現職
・日本糖尿病学会専門医、指導医
・専門分野:老年医学、糖尿病、病態栄養
内容
受講対象:CDEJになりたての方からベテランの方まで(職種問わず)。
▼わが国では超高齢化社会を迎え、高齢者糖尿病が増加の一途を辿っています。加齢とともに糖尿病合併症や併発症も多くなるため、治療の際は注意が必要です。
▼また、高齢であっても、糖代謝異常や心身機能障害の程度は個人差が大きく、きめ細やかな工夫を伴う個別対応が必要です。
▼本コースでは、高齢者糖尿病の療養指導について、低血糖への対処法、認知機能やフレイルとの関連、薬物選択に至るまで、最新の知識を織り込みつつ体系的に学ぶことを目的に、荒木厚先生よりわかりやすくご講演をいただいております。
知識の整理、アップデートにお役立てください。
開講状況
2018年11月開講
高齢者糖尿病の薬物療法
講師
深野 光司(CDEJ、東京都立府中療育センター 薬剤科)
・一般社団法人臨床糖尿病支援ネットワーク評議員
・2004年 CDEJ 認定取得
・2003年 西東京糖尿病療養指導士 認定取得
・2009年 NST専門療法士 認定取得
内容
受講対象:CDEJになりたての方からベテランの方まで(職種問わず)。
▼高齢者糖尿病の薬物療法へのかかわり方、注意すべき点について解説されています。
▼高齢糖尿患者は罹病歴の長期化により、病態が複雑になる場合もあり、また認知機能の低下もみられます。よりよい糖尿病薬物療法を実践するためのきめ細かい対応について学習していただけます。
▼高齢糖尿病患者への薬物療法の実践について、具体的な方法も解説されています。ぜひ、明日からの療養指導にお役立てください。
■補足資料があります。受講される方は「受講にあたっての注意事項」画面でダウンロードしてご確認ください。(2023年11月)
開講状況
2018年11月開講
糖尿病足病変の病態・診断・治療
講師
渥美 義仁(永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター長)
・1977年 慶応義塾大学医学部卒業
・東京都済生会中央病院 内科部長、糖尿病臨床研究センター長を歴任
・2013年 永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター長
・日本糖尿病学会専門医・指導医
・専門分野:糖尿病の足病変とその予防的フットケア、血糖自己測定の活用など
内容
推奨受講対象:CDEJになりたての方からベテランの方まで(職種問わず)。
▼日本は世界と比べて足の診察の実施率が低いことが分かっています。実際に足病変・足潰瘍の症例をフォローされている方はどれくらいいるでしょうか?
▼突然、足病変の患者が来院した場合でも、適切な対応や処置ができるよう、実際の足の写真を示しながら解説していただきました。
▼足病変がどのようなものかを理解し、患者にそれを伝えることで、合併症予防という目的に向かってより積極的に治療に取り組んでいただくことにも繋がります。
▼足病変の基礎から応用までを網羅しています。ぜひご視聴ください。
開講状況
2019年5月開講
血糖コントロールの指標と目標値
講師
佐藤 麻子(東京女子医科大学医学部 臨床検査科)
・1983年 東京女子医科大学卒業 同糖尿病センター入局
・1995-1998年 ステノ糖尿病センター留学
・2000年 東京女子医科大学糖尿病センター講師
・2008年 東京女子医科大学臨床検査科・糖尿病センター兼務 准教授
・2012年 東京女子医科大学臨床検査科・糖尿病センター兼務 教授
内容
受講対象:CDEJになりたての方からベテランの方まで(職種問わず)。
▼患者さんから「ヘモグロビンエーワンシーってなんですか?1.5エージーってなんですか? ジーエーってなんですか?」と聞かれたら、どのように対応しますか?
▼普段何気なく使用している糖尿病の臨床検査値について、あらためて学習いただけるセッションです。
▼臨床検査の結果を適切に読み解くことは、その特徴を理解していないとできません。糖尿病以外の併発疾患によっては、血糖値との乖離が出てしまうこともあります。
▼このセッションでは、診断から治療目標値、検査値がどのように測定されるかまでしっかり学習していただけます。知識に少し自信がない方も、よく理解している方の復習としてもご活用ください。
開講状況
2019年5月開講
糖尿病患者のフットケアの基本
講師
加藤 理賀子(CDEJ、川崎市立川崎病院)
・1982年~ 川崎市立川崎病院 勤務
・2001年 CDEJ 認定取得
・2004年 糖尿病看護認定看護師 取得
・日本下肢救済・足病学会創立時より理事4期、現在は評議員
内容
看護師が行う糖尿病患者のフットケアは、足病変の発症予防と再発予防に向けた患者教育を実践することにあります。またフットケアは、足だけにとどまるのではなく、足を通して糖尿病療養全体を支援する側面もあります。
▼本講義では、フットケアはなぜ大切なのか、フットケアのためのアセスメント、足の観察方法や患者指導、フットケアの実際について、フットケアの基本をご説明します。
▼フットケアの実際については、ポイントを解説しておりますので、フットケアを始めたいという看護師や、療養支援の一つとして学びたいという方にも、職種を超えて学べる内容になっています。
▼渥美義仁先生の「糖尿病足病変の病態・診断・治療」と併せての受講をお勧めします。
開講状況
2019年5月開講
糖尿病患者における高血圧管理
講師
片山 茂裕(埼玉医科大学 かわごえクリニック院長)
・1973年 東京大学医学部卒業、同第三内科入局
・1983年 埼玉医科大学第四内科講師を経て、1989年 同 助教授
・1995年 同 教授(内分泌・糖尿病内科)
・2008年 同大学病院 病院長
・2014年 同大学かわごえクリニック 院長
・主に糖尿病患者の高血圧や糖尿病腎症の研究を行っている。
内容
受講対象:CDEJになりたての方からベテランの方まで(職種問わず)。
▼高血圧には様々なパターンがあります。同じ血圧でも、どのように推移していたかを知っておくことは、血圧コントロールをする上で大切です。
▼日本人は食塩感受性が高い人種です。高血圧の予防、良好なコントロールのためには、特に塩分摂取には気をつけなければなりません。
▼本コースでは、糖尿病患者の高血圧管理についてあらためて学習いただける内容となっています。食事や塩分摂取に限らず、高血圧をもたらす因子や注意点についてまとめていただき、翌日からの療養指導で活用できる知識を身につけることができるセッションです。
▼2019年4月に出版された「高血圧治療ガイドライン2019」についても解説しています。
開講状況
2019年7月開講
糖尿病の脂質異常症管理
講師
石橋 俊(自治医科大学 内科学講座 内分泌代謝学部門)
・1982年 東京大学医学部医学科卒業
・1989年 University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Department of Molecular Genetics留学
・1994年 東京大学医学部附属病院第3内科 助手
・2001年 自治医科大学内科学講座内分泌代謝学部門 教授
内容
推奨受講対象:中堅からベテランの方向け(脂質異常症管理 応用レベル)。
▼脂質異常症について、奥深く学ぶことができます。代謝や機序、遺伝子異常におけるLDL蓄積の違い、身体所見についても細かく解説いただきました。
▼2型糖尿病での脂質異常症の特徴、影響についても解説されています。治療においては各薬剤の特性と副作用、新しい薬剤の実際まで、余すことなく学べます。
▼このセッションを理解すれば、脂質異常症管理のスペシャリストにさらに近づくことができます。
▼脂質についてより深く学びたいとお考えの方には特に、繰り返し視聴していただきたいセッションです。
開講状況
2019年7月開講
カーボカウントのポイント 基礎編 / カーボカウントのポイント 応用編
講師
黒田 暁生(徳島大学 糖尿病臨床・研究開発センター)
・1982年 1型糖尿病発症
・1995年 東京医科歯科大学医学部卒業
・2011年 徳島大学 助教(糖尿病臨床・研究開発センター)
・2016年 徳島大学 准教授(先端酵素学研究所)、現在に至る
内容
【基礎編】
これまで長く、食品交換表をベースとした食事療法が行われてきましたが、カーボカウントという方法が食事療法の選択肢に加わったことにより、患者の食事療法の自由度は広がりました。一方で、糖質制限食とカーボカウントの考えを混同されているケースもあり、適切な療養指導が重要です。
▼【基礎編】では、黒田先生がわかりやすく基礎的な考え方を解説してくださいます。
▼本コースで学習していただく「基礎カーボカウント」は、糖尿病患者に広く汎用できる知識です。既に、カーボカウントを用いて療養指導にあたっているCDEJは多いと思いますが、ぜひ、この機会に基本を再確認しましょう。
▼【応用編】を受講される方も、まず【基礎編】からの受講をお勧めします。
【応用編】
カーボカウントという方法が食事療法に加わったことによって、食事療法の選択肢が広がり、患者の自由度は広がりました。実際の医療現場では、(管理)栄養士に限らず、いろいろな職種のCDEJがカーボカウントに関する療養指導を行うシーンが増えていると思います。
▼「応用カーボカウント」は、インスリン治療を行っている糖尿病患者を対象としたものです。【基礎編】に続き、黒田先生が実例を通して具体的にわかりやすく解説してくださいます。
▼加えて、外食でのカーボカウントについても説明していただきました。
▼【基礎編】と併せての受講をお勧めします。
開講状況
2019年9月開講
2型糖尿病におけるインスリン治療 -患者背景を考慮したオーダーメイド治療-
講師
吉岡 成人(NTT東日本札幌病院 院長)
・1981年 北海道大学医学部卒業
・聖路加国際病院、自治医科大、朝日生命糖尿病研究所、市立札幌病院にて勤務。
・2003年 北海道大学大学院医学研究科病体代謝内科学講座第二内科 助教授
・2008年 北海道大学病院第二内科診療教授
・2011年 NTT東日本札幌病院内科診療部長、副院長を経て
・2018年 NTT東日本札幌病院院長
内容
受講対象:CDEJになりたての方からベテランの方まで(職種問わず)。
▼高齢者、認知症、低血糖、インスリン治療の受け入れ、血糖管理など、インスリン治療に関する様々な問題をクリアにご解説いただいているセッションです。
▼“Clinical Inertia(クリニカルイナーシャ)”が起こらないためには、我々医療者が持つ”バイアス”と、患者さんがどう感じているのかについても分かりやすくご解説いただいています。
▼インスリン治療を実施していく中で起こる問題と血糖コントロールの理想と現実についてもご提示いただいていますので、CDEJの皆様がいつも感じている問題点の解決の一助となるかもしれません。
▼インスリン治療に関しての学習として、非常に勉強になるセッションです。ぜひご視聴ください。
開講状況
2019年12月開講
糖尿病腎症の診断と治療
講師
古家 大祐(金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学 教授)
・1984年 滋賀医科大学医学部医学科卒業、滋賀医科大学医学部附属病院第三内科入局
・1989年 滋賀医科大学医学部附属病院第三内科 医員。1992年 助手
・1994年 ジョスリン糖尿病センター 研究員
・1997年 滋賀医科大学医学部附属病院第三内科 助手
・2004年 滋賀医科大学医学部附属病院内科 講師
・2005年 金沢医科大学内分泌代謝制御学 教授
・2010年より現職(講座名変更)
内容
受講対象:CDEJになりたての方からベテランの方まで(職種問わず)。
▼糖尿病腎症は透析導入に至る原因疾患として第1位ですが、その割合はようやく横ばいから減少傾向になってきました。
▼“糖尿病透析予防管理”を積極的に行っている施設も多いかと思いますが、改めてその重要性や診断、治療について分かりやすくご解説いただきました。
▼糖尿病腎症から透析になる可能性があると知ると、患者さんも大きなショックを受けることでしょう。早期の治療や適切な管理により腎症の進行を遅らせることができるなど、知識を整理し、患者さんに正しい情報を伝えられるようになる機会としてご活用ください。
▼糖尿病腎症の診断から治療、そして栄養管理まで学習していただけるセッションです。ぜひご視聴ください。
開講状況
2019年12月開講
糖尿病運動療法のアート(その1)
講師
天川 淑宏(CDEJ、東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科)
・理学療法士、健康運動指導士、日本体力医学会健康科学アドバイザー、日本ノルディックフィットネス協会公認指導員、全日本スキー連盟公認準指導員
・おもな経歴:早稲田大学社会科学部、学校法人医学アカデミー理学療法学科、西武ライオンズ(広岡監督時代)で水特性を活用したオフトレ担当、朝日新聞社関連事業部でフィットネス施設開設と運営
・2002年~現在 東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科
・研究領域:糖尿病運動療法 運動器リハビリテーション
内容
受講対象:CDEJになりたての方からベテランの方まで(職種問わず)。
▼「心が動いて、体が動きたくなる」、そんな状態に患者さんがなってもらうための”ヒント”を学べるセッションです。
▼糖尿病患者さんは糖尿病治療において運動することが非常に大切であることを知っています。しかし、「膝が痛い、時間がない、運動は苦手で…」と言い、なかなか実践や継続が難しい患者さんも多いことは、CDEJの皆さんも経験されていることでしょう。
▼このセッションでは、具体的な運動療法をご提示いただき、明日からの療養指導から使える内容ばかりです(有酸素運動、ストレッチング運動、レジスタンス運動)。
▼天川先生による糖尿病運動療法のコースは、いろいろなテーマで順次制作し、公開予定です。このセッションはその1本目です。
▼写真やイラストも多いので、視聴しながら実際に体を動かしてみてはいかがでしょうか。Let’s try it!!
開講状況
2020年1月開講
2型糖尿病と服薬アドヒアランス
講師
堀井 剛史(CDEJ、北里大学薬学部 薬学治療学I)
・2002年 星薬科大学卒業、東京女子医科大学病院 薬剤部入局
・2006年 東京都済生会中央病院 薬剤部入局
・2016年 下北沢病院 薬剤部 薬剤部長
・2016年 武蔵大学薬学部薬物動態学研究室 客員研究員 (兼務)
・2018年 北里大学薬学部薬物治療学Ⅰ 助教、現在に至る
内容
受講対象:CDEJになりたての方からベテランの方まで(職種問わず)。
▼2型糖尿病の治療は食事・運動・薬物療法から成り立ちますが、目標の血糖値を達成するためのカギは、いかにして治療のアドヒアランスを高く保つことができるかにかかっています。
▼このセッションでは、特に糖尿病薬物療法のアドヒアランスに注目し、2型糖尿病の服薬アドヒアランスの現状、服薬アドヒアランスに影響を与えるものはどのようなものがあるか、さらに服薬アドヒアランスを向上させるために我々は何をすべきかについて、わかりやすく解説しています。
▼服薬アドヒアランスを向上させるための取り組みについて、具体的にわかりやすく解説されていますので、実際の臨床現場でも活用していただけます。
▼服薬アドヒアランスについて考える第一歩として、最適なセッションです。ぜひご視聴ください。
開講状況
2020年1月開講
糖尿病注射薬の療養指導 -自己注射指導のプラクティス1-(基礎編)
講師
朝倉 俊成(CDEJ、新潟薬科大学薬学部 教授)
・1989年3月 太田綜合病院薬剤部勤務
・1996年4月 太田西ノ内病院薬剤部勤務 薬局長補佐
・2006年4月 新潟薬科大学薬学部臨床薬学研究室 准教授
・2006年4月〜2007年6月 新津医療センター病院 薬剤部長(兼務)
・2009年3月〜現在 京都医療センター予防医学研究室 研究員
・2012年4月〜現在 新潟薬科大学薬学部臨床薬学研究室 教授
・2015年4月〜現在 新潟大学(医学系)客員研究員
内容
受講対象:CDEJになりたての方からベテランの方まで(職種問わず)。
▼有効性、安全性、経済性を踏まえてインスリン注射を選択した上で、適正な注射手技を身に着けることが、適正なインスリン治療を行う上で重要になります。
▼このセッションでは、インスリン注射を実践する上で、インスリン注射の組み立てから後片付けまで、一連の注射手技について図表などを用いながらとても分かりやすく解説されています。
▼インスリン注射の指導に必要な基本的な知識から、患者さんに上手に説明するためのワンポイントアドバイスまで、具体的にわかりやすく解説されていますので、実際の臨床現場で重宝する内容になっています。
▼書籍にはない、かゆいところに手が届く内容が盛りだくさんです。ぜひご視聴ください。
開講状況
2020年2月開講
経口血糖降下薬治療
講師
田尻 祐司(久留米大学 内分泌代謝内科)
・1984年 九州大学医学部卒業 同第3内科(現病態制御内科)入局
・1994年~1996年 スウェーデン王立カロリンスカ研究所留学
・2007年 久留米大学医学部内分泌代謝内科 准教授
・2018年 久留米大学医学部内分泌代謝内科 教授
・2019年 久留米大学医療センター糖尿病センター 教授
内容
対象:CDEJになりたての方からベテランの方まで(職種問わず)
▼現在上市されている糖尿病の経口薬の種類は、大きく分けて7種類あります。
▼実際に発売されている薬剤は1種類につき1剤というわけではなく、何剤か上市されている現状です。それぞれの薬剤ごとに異なる特徴、服薬回数、使用上の注意、用量調節の必要があります。
▼田尻先生からは、経口薬の作用機序から注意点、副作用をご解説いただきました。
▼薬剤に関する最新のエビデンスの解説もありますので、ぜひご視聴ください。
開講状況
2020年2月開講
J-DOIT3から学ぶ2型糖尿病の治療戦略
講師
門脇 孝
(東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・生活習慣病予防講座 特任教授/
帝京大学医学部附属溝口病院 病態栄養学講座 常勤客員教授)
・1978年 東京大学医学部医学科卒業
・1980年 東京大学第三内科 糖尿病グループ
・2003年 東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科 教授
・2011年~2015年 東京大学医学部附属病院長
・2018年より同 糖尿病・生活習慣病予防講座特任教授、帝京大学医学部附属溝口病院病態栄養学講座常勤客員教授
・主に2型糖尿病の成因と治療の研究を行っている。
内容
対象:CDEJになりたての方からベテランの方まで(職種問わず)
▼J-DOIT3は、複数の危険因子の安全な正常化が日本人2型糖尿病患者の健康寿命・QOLをどれだけ改善するかをみた大規模臨床試験です。血糖や血圧・脂質に加えて、生活習慣へのより強力な介入(食事・運動・禁煙・教育など)の、合併症抑止効果について調査しています。
▼今回は、J-DOIT3の研究リーダーを務められた門脇孝先生から、J-DOIT3の意義と結果について解説いただきました。
▼J-DOIT3を理解し、その結果を今後の日本人の糖尿病療養支援にどう活かすかを考えることが、説得力のある支援に繫がると思います。
▼本機構設立20周年の節目の企画として、また、日本人糖尿病の療養指導の礎となる知識の習得のため、すべてのCDEJの方に受講していただきたいコ―スです。
開講状況
2020年2月開講
SMBG・CGMの活用法
講師
西村 理明(東京慈恵会医科大学 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科)
・1991年 東京慈恵会医科大学卒業
・1998年 Graduate School of Public Health, University of Pittsburgh修了(MPH取得)
・2000年-2002年 富士市立中央病院 内科医長
・2000年-2016年 Adjunct Assistant Professor, Graduate School of Public Health, University of Pittsburgh
・2002年-2006年 東京慈恵会医科大学・糖尿病・代謝・内分泌内科 助手
・2006年-2011年 同 講師 2011年-2018年 同 准教授
・2019年-現在 同 講座担当教授
内容
対象:CDEJになりたての方からベテランの方まで(職種問わず)
▼2018年12月1日からリアルタイムCGMが保険適用になり、日本糖尿病学会では「リアルタイムCGM適正使用指針」を作成しました。
▼Jスキルコースでは、日本糖尿病学会の「リアルタイムCGM適正使用のためのeラーニング」で講師を務められた西村先生から、SMBGやCGMを用いて測定した血糖値をどのように読み解くかについて、CDEJ向けにわかりやすくご解説いただきます。
▼血糖測定ができる医療機器は進化を続けています。しかし、いくら便利になったとしても、それをどのように活用すればよいかを理解していなければ役にも立ちません。
▼このセッションでは、実際のCGMデータなどをお示しいただきながら、データを読み解くポイントを学べるセッションとなっています。
▼新しい機器の紹介もありますので、ぜひご視聴ください。
開講状況
2020年4月開講
食品交換表に基づいたカーボカウント法
講師
高橋 徳江(CDEJ、順天堂大学医学部附属浦安病院 栄養科)
・女子栄養大学卒業後、順天堂大学医学部附属順天堂医院栄養部勤務
・2001年 CDEJ 認定取得
・2010年 順天堂大学医学部附属練馬病院栄養科へ異動
・2015年 糖尿病病態栄養専門管理栄養士 認定取得
・2018年 順天堂大学医学部附属浦安病院栄養科へ異動、現在に至る。
内容
対象:CDEJになりたての方からベテランの方まで(職種問わず)
▼「カーボカウントに興味はあるけど、糖質量の計算や使い方が難しいのでは?」と不安を感じていませんか? このセッションで一緒に学習しましょう。
▼「食品交換表」に基づいたカーボカウントの基礎から指導のポイントまで、分かりやすく解説していただきました。
▼管理栄養士の立場から、他職種の方にも理解しやすく実際の患者への説明・指導に使える表現もまじえてお話しいただき、日々の指導にすぐいかせる内容となっています。
▼カーボカウントについて学んでみたい、もう一度学びなおしたい、とお考えの皆さんに、ぜひ受講いただきたいセッションです。
開講状況
2020年5月開講
糖尿病の食事療法
講師
本田 佳子(CDEJ、女子栄養大学)
・1983年 女子栄養大学卒業
・1986年 虎の門病院 栄養部 第5科長
・1992年 同 副部長
・1996年 同 栄養部部長
・2004年 女子栄養大学栄養学部・女子栄養大学大学院栄養学研究科 教授
・2007年 東北大学大学院医学研究科博士後期課程修了、医(障害)学博士
内容
対象:CDEJのなりたての方からベテランの方まで
▼このコースでは、2019年に改訂された「糖尿病診療ガイドライン2019」における栄養食事療法のポイントについて講義されています。
▼特に、従来の標準体重から新たに「目標体重」という概念が取り入れられましたが、この点も含め、摂取エネルギー量の適正化、フレイルについて丁寧に解説いただいています。
▼栄養指導の目標設定として「食事療法の効果指標」や「栄養管理到達目標」を示された上で、ケーススタディでは、どのように栄養アセスメントをし、計画し、介入するか、療養指導の実際についてお話しいただきました。ぜひご視聴ください。
※ 本コースでとりあげるケーススタディは、本機構主催「認定更新者用講習会」ケース2の症例データを用いて、食事療法に特化して解説しています。
開講状況
2020年8月開講
糖尿病治療における運動療法の意義と療養指導の在り方
講師
細井 雅之(地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 糖尿病内分泌センター長・糖尿病内科部長)
・1987年 大阪市立大学医学部卒業
・1991年 大阪市立大学医学部大学院修了、米国ボストン大学心血管研究所留学
・1995年 大阪市立大学医学部第2内科 助手
・2007年 大阪市立総合医療センター 代謝内分泌内科 部長、栄養部 部長
・2014年10月~ 現職
・2020年9月現在
日本臨床スポーツ医学会理事、日本内科学会指導医、認定内科医、日本糖尿病学会学術評議員、指導医、専門医、日本内分泌学会内分泌代謝科指導医、専門医、日本糖尿病合併症学会評議員、日本臨床運動療法学会評議員、日本病態栄養学会評議員
内容
実臨床の運動療法の課題を踏まえ、医師の立場から「糖尿病診療ガイドライン2019」における運動療法について解説していただきました。
▼運動の意義とサイエンスを療養指導で活用できるように解説されており、まさに ”運動療法の electronic バイブル” と言える内容です。ぜひご視聴ください。
開講状況
2020年11月開講
糖尿病足病変の爪や皮膚のケア(基礎編 / 実践編)
講師
鈴木 由加(千葉県循環器病センター 看護部)
・2003年 皮膚・排泄ケア認定看護師(旧 WOC看護認定看護師)取得
・2017年 日本看護協会 特定行為研修受講(創傷モデル)
・2014年~千葉県循環器病センター 継続看護統括上席看護師長
・弾性ストッキング・コンダクター
・日本下肢救済・足病学会 認定師
・日本創傷・オストミー・失禁管理学会 評議員
・日本フットケア 足病医学会 評議員
内容
糖尿病足病変の予防には、血糖コントロールに加え、日常的な足の健康管理「フットケア」が欠かせません。「足の観察と清潔を保つ」という基本的なフットケアの日々の実践が必要です。
▼足は他の皮膚とは異なる独特の構造をしており、人が立ったり歩いたり走ったりするとき、重要な役割を果たしています。運動療法の継続のためにも、フットケアが重要と言われるのはそのためです。しかし、糖尿病患者は神経障害と血流障害により、その構造が保たれず足病変を起こしやすい状況にあります。
▼今回、皮膚ケアのスペシャリストである鈴木先生から糖尿病足病変とそのケアについて解説していただきました。
【基礎編】
皮膚の構造と機能、足の皮膚と爪の特徴から、詳しくお話しいただきました。まずCDEJが理解し、患者に情報提供することによって、患者のセルフケア能力の向上が期待できます。
【実践編】
より具体的なケアの実際として、糖尿病足病変予防・重症化予防、静脈性下肢潰瘍とケアの他、症例について解説いただきました。
▼明日の療養指導につながるエッセンスがたくさん詰まったコースです。看護師だけでなく、理学療法士や管理栄養士、臨床検査技師、薬剤師の方々にも聴講していただきたいコースです。
開講状況
2021年9月公開
糖尿病網膜症(眼科医の立場から)
講師
北野 滋彦(東京女子医科大学糖尿病センター 教授)
・1982年 日本大学医学部医学科卒業、東京大学医学部眼科学教室入局
・1988年 東京女子医科大学糖尿病センター眼科 講師
・1990年~1993年 米国エール大学眼科
・1995年 東京女子医科大学糖尿病センター眼科 助教授
・2000年 東京女子医科大学糖尿病センター眼科 教授
内容
対象:療養指導のレベルUP、一歩踏み込んだ知識習得を目指す方(職種問わず)。
▼CDEJの皆様は、眼科で実際にはどのような診察・治療がなされているか、ご存じですか。また、患者さんにはどのように説明していますか。
▼糖尿病三大合併症といわれる「し・め・じ」の「め」というと糖尿病網膜症をイメージされる方が多いのではないでしょうか。視力低下の原因となる糖尿病眼合併症は、糖尿病網膜症だけではありません。
▼本セッションでは、糖尿病の眼に対する様々な影響や糖尿病網膜症の診断~治療について詳細に学ぶことができます。療養指導のさらなる高みを目指す方に、ぜひ受講いただきたい内容です。
開講状況
2022年2月公開
日常診療で行う糖尿病性神経障害の診断と治療
講師
成瀬 桂子(愛知学院大学歯学部 内科学講座 主任教授)
・1988年 名古屋大学医学部卒業
・1990年 名古屋大学大学院医学系研究科博士課程
・1995年 名古屋大学医学部附属病院 第三内科学講座 医員
・1998年 ハーバード大学医学部、ジョスリン糖尿病センター 博士研究員
・2004年 愛知学院大学歯学部 内科学講座 講師、2006年 同准教授
・2021年 愛知学院大学歯学部 内科学講座 主任教授
内容
対象:糖尿病療養指導士の初心者からベテランの方まで(職種問わず)
▼「糖尿病性神経障害」が糖尿病三大合併症の1つであることを、CDEJの皆さんはよくご存じのことと思います。しかし、患者さんはどうでしょうか? 痛みの症状がなければ気にもかけず、自分に神経障害があるかどうかも知らない方が多いことも事実です。
▼このセッションでは、療養指導に必要な糖尿病性神経障害の知識を、病態・診断・治療とケアの点から解説していただきました。知識のブラッシュアップ、さらなるスキルアップに役立つ内容となっています。ぜひご視聴ください。
開講状況
2022年3月公開
糖尿病と神経精神疾患
講師
佐倉 宏(東京女子医科大学附属足立医療センター 副院長/内科部長/教授)
・1982年 東京大学医学部医学科卒業
・1991年 東京大学附属病院第三内科文部教官 助手
・1994年 オックスフォード大学生理学研究室 Research Scientist
・1999年 東京女子医科大学糖尿病センター 講師(2007年 准教授)
・2012年 東京女子医科大学東医療センター 内科教授
・2022年 病院移転に伴い、所属先名変更
・専門:2型糖尿病の成因・治療、医療情報解析
内容
対象:一歩踏み込んだ知識を習得し、療養指導のレベルUPを目指す方(職種問わず)
▼糖尿病に関連する疾患として、近年、認知症、うつ病、不安障害、摂食障害、統合失調症などの神経精神疾患が注目されています。病因や治療法はそれぞれ異なりますが、併発すると糖尿病の療養支援が容易でなくなる点については、共通しています。
▼このセッションでは、「統合失調症に合併する肥満・糖尿病の予防ガイド」(2020年刊行)に3学会合同の作成委員会メンバーとして参画された佐倉先生から、糖尿病と様々な神経精神疾患との関係や特徴について、網羅的に解説していただきました。
▼精神疾患を併存する糖尿病患者の療養支援について、注意すべき点は何か、またどのような困難があるか、ぜひ考えてみてください。
開講状況
2022年4月公開
糖尿病性腎症の食事療法
講師
市川 和子(岡山県栄養士会医療事業部)
・1976年 川崎医科大学附属病院栄養部就職
・1978年 管理栄養士取得
・2001年 CDEJ取得
・2003年 病態栄養認定管理栄養士取得
・2006年 日本病態栄養学会NSTコーディネーター
・2013年 川崎医科大学附属病院栄養部部長
・2016年 腎臓病病態栄養専門管理栄養士取得
・同年 川崎医療福祉大学臨床栄養学科特任准教授(~2021年)
内容
糖尿病治療の目的は合併症の予防と進展防止にあり、療養指導はそれを支えるものでなくてはなりません。
▼合併症のうち糖尿病性腎症は、わが国の透析導入の主たる原因疾患であることは特記すべき点です。糖尿病性腎症を合併させないこと、そして、合併した場合はその進行を遅らせ透析導入を防止することが、療養指導における重要課題です。
▼糖尿病性腎症の療養において食事療法は欠かせませんが、療養指導では患者個々の状況に応じた対応が必須であり、塩やたんぱく質の調整、状況によりカリウムの制限も必要です。たんぱく質制限の過程では摂取エネルギー不足が生じやすい状況となり、その対処も必要となります。
▼「糖尿病の食事療法」から「糖尿病性腎症の食事療法」へのシフトに戸惑う患者も多く、具体的な療養指導が期待されています。本講義では、糖尿病性腎症の食事療法について、理論から実践まで具体的に解説しています。
開講状況
2022年7月公開
糖尿病とがん
講師
大橋 健(国立がん研究センター中央病院 総合内科(糖尿病腫瘍科)科長)
・1992年 東京大学医学部卒業
・1999年 東京大学大学院医学系研究科修了・医学博士(内科学)
・2003年 東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 助手
・2007年 同 特任講師
・2010年~ 国立がん研究センター中央病院 総合内科 科長
がん専門病院において、糖尿病を持ちながらがん治療に取り組む患者・がん治療中に新たに糖尿病を発症した患者の診療に従事。
日本糖尿病学会・日本癌学会による「糖尿病と癌に関する委員会」委員。
編著に『腫瘍糖尿病学Q&A がん患者さんの糖尿病診療マニュアル』(金芳堂)など。
内容
対象:糖尿病療養指導士になりたての方からベテランの方まで(職種問わず)
▼2人に1人はがんになる時代です。また、糖尿病がある人の死因の第1位はがんです。
▼この2つの疾患が同時にある状態になったとき、患者自身の希望も踏まえて治療に向き合うことになります。CDEJの皆さんの支えは、患者にとってとても大切です。
▼CDEJであるすべての方に知っておいていただきたい内容です。
開講状況
2023年4月公開
糖尿病運動療法のアート(その2)
講師
天川 淑宏(CDEJ、東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科)
・理学療法士、健康運動指導士、日本体力医学会健康科学アドバイザー、日本ノルディックフィットネス協会公認指導員、全日本スキー連盟公認準指導員
・おもな経歴:早稲田大学社会科学部、学校法人医学アカデミー理学療法学科、西武ライオンズ(広岡監督時代)で水特性を活用したオフトレ担当、朝日新聞社関連事業部でフィットネス施設開設と運営
・2002年~現在 東京医科大学八王子医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科
・研究領域:糖尿病運動療法 運動器リハビリテーション
内容
受講対象:CDEJになりたての方からベテランの方まで(職種問わず)。
▼「心が動いて、体が動きたくなる」、そんな状態に患者さんがなってもらうための”ヒント”を学べるセッション”Part2”です。
▼今回のセッションでは、ストレッチング運動の意義、指導のポイントについてご紹介します。
▼「ストレッチングって、運動療法になるの??」と思われるかもしれませんが、侮ってはいけません。強度の強い運動は難しいけれどストレッチングなら…と思う患者さんも多いのではないでしょうか。
▼ストレッチングの指導時のポイントを含めて具体的な方法を、イラストで分かりやすく解説していただいております。視聴しながら実際に体を動かしてみてはいかがでしょうか。Let’s try it!!
開講状況
2023年5月公開
糖尿病治療の現状と問題点(体の仕組みから考える)
講師
植木 浩二郎(国立国際医療研究センター研究所 糖尿病研究センター)
・1987年 東京大学医学部医学科 卒業
・1989年 東京大学医学部第三内科 入局
・1997年 Harvard 大学 Joslin Diabetes Center ポストドクトラルフェロー
・2001年 同 Instructor
・2004年 東京大学大学院医学系研究科 21 世紀 COE プログラム 特任助教授
・2007年 東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・代謝内科 准教授
・2014年 東京大学大学院医学系研究科 分子糖尿病科学講座 特任教授
・2016年 国立国際医療研究センター研究所 糖尿病研究センター長
・2020年 国立高度専門医療研究センター 医療研究連携推進本部長(兼任)
・2020年 東京大学大学院医学系研究科 分子糖尿病学講座教授(兼任)
内容
対象:糖尿病療養指導士になりたての方からベテランの方まで(職種問わず)
▼日本糖尿病学会理事長の植木浩二郎先生から、なぜ糖尿病になってしまうのかを体の仕組みから考え、分かりやすく解説していただきました。
▼2022年には2型糖尿病治療のアルゴリズムが発表されましたが、そのコンセプトやポイント、現行の治療薬の問題点についても触れられています。
▼CDEJの皆さんにも糖尿病治療の現状と問題点をご理解いただき、必要なサポートはどんなことかを一緒に考える機会としていただければと思います。
開講状況
2023年6月公開
糖尿病合併妊娠
講師
荒田 尚子(国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター 母性内科診療部長)
・1986年 広島大学医学部卒業、広島大学医学部附属病院内科 研修医
・1987年 慶應義塾大学医学部内科研修医を経て内科学・腎臓内分泌代謝科 助手
・1995年 横浜市立市民病院内科(糖尿病内科)
・2001年 米国マウントサイナイ医科大学内分泌糖尿病骨疾患科 留学
・2004年 国立成育医療研究センター総合診療部医師
・2010年より現職
・日本糖尿病学会専門医、指導医
・専門分野:周産期内科、糖尿病、内分泌代謝
内容
対象:糖尿病療養指導士になりたての方からベテランの方まで(職種問わず)
▼妊娠時の高血糖は胎児の先天奇形の原因となります。挙児希望の糖尿病患者さん、妊娠中の明らかな糖尿病を指摘された妊婦さんは大きな不安を覚えるかもしれません。
▼本セッションでは、食事や運動、どのように血糖マネジメントをしていけばよいかなど、糖尿病合併妊娠について分かりやすくご解説いただいています。
▼CDEJとして、あらためて正しい知識を習得し、患者に寄り添った療養指導ができるよう、ぜひご受講ください。
開講状況
2023年6月公開
公開終了したコース
糖尿病腎症重症化予防における看護師の役割(講師:金井 千晴)2018年11月公開 ※2023年3月31日公開終了 →詳細はこちら
糖尿病腎症重症化予防における看護師の役割
講師
金井 千晴(CDEJ、東京歯科大学市川総合病院)
・聖路加看護大学卒業
・東京女子医科大学病院糖尿病センター勤務を経て、2004年より日本看護協会看護研修学校 認定看護師教育専門課程 糖尿病看護学科専任教員。
・2007年 日本赤十字看護大学修士課程入学、成人看護学(慢性看護領域)専攻。同年より、東京歯科大学市川総合病院に勤務。
・看護師、保健師、衛生管理者。CDEJ 認定(2001年)、慢性疾患看護専門看護師 取得(2011年)
内容
わが国においては、高齢化が進む中で生活習慣と社会環境の変化に伴う糖尿病患者数の増加が課題になっています。
▼糖尿病の合併症は患者のQOLを著しく低下させるのみならず、医療経済的にも大きな負担を社会に強いることが予測され、2016年、日本医師会・日本糖尿病対策推進会議および厚生労働省は、全国で糖尿病性腎症重症化予防に向けた取組を始めました。
▼そのような中、速やかに糖尿病性腎症重症化予防のためのプログラムを策定するため、それぞれの地域での取り組みが始まっています。 これらの動きよりも前から、慢性疾患看護専門看護師として腎症重症化予防に取り組んでこられた金井千晴先生から、看護師の役割についてご講演をいただきました。
▼これから取組を始める方や今まさに始めようとしておられる方、また看護師だけでなくすべてのCDEJの方々にとって具体的かつ興味深い内容になっています。